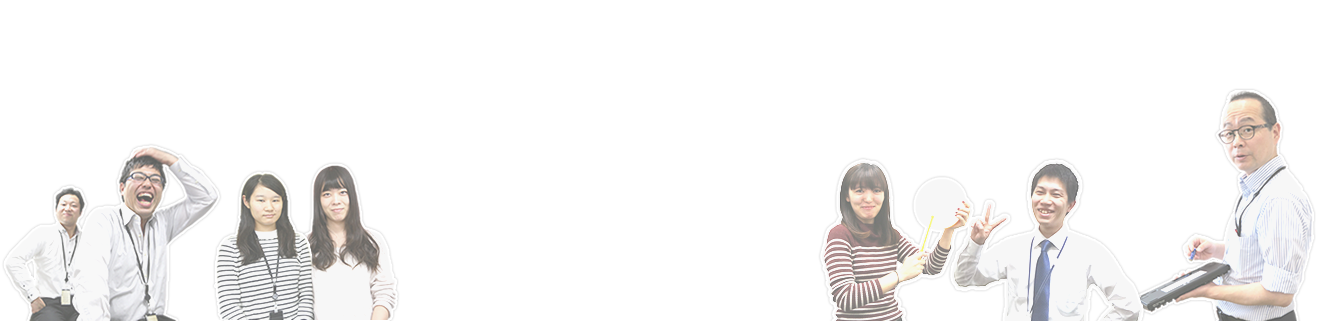捨てない本
こんにちは、法人満足室の義夫です。
皆さん、古い本ってどうされてます!?
自分の中で、もう読まないだろーなーに分類された本は、古本屋さんで処分してきましたが、いったんは読まないであろうに分類されても心に残る本はずっと取ってきました。
今回のブログでは、そんな生き残った本の中から一冊照紹介したいと思います。
本のタイトルは「F1地上の夢」です。もうお亡くなりになられてますが、海老沢泰久さんが執筆されてF1ブーム初期の1987年に出版されました。

ホンダF1の一~二期について書かれた本なのですが、今のように洗練はされてなく、もっと素朴に人がマシンを操って速さを競う時代のお話です。
そして物語の主役はレーサーではなく、パワーのあるエンジンを創ることに情熱を傾けた技術者たちです。
第一期のF1活動は、監督は中村良夫、ドライバーはロニーバックナムの布陣でスタートしますが、全てが初めてのことで、悪戦苦闘の連続です。乗り越えても乗り越えても何度も襲ってくる試練に時に負けそうになりながらもへこたれず、逆に闘志を燃やして抗い、立ち向かう姿が胸を打ちます。
何故この本が古本屋に島流しにあわないかというと、読むたびに涙してしまうシーンがあるからです。
場面は、F1参加の第一戦目、ドイツ・グランプリ。
ルールでは、予選中にコースを5週しなければならないのですが、
ホンダF1マシンは4週を走ったところでマシントラブルに見舞われ
ピットから出ることが出来ません。5週を走り切ることは絶望的な
状況です。つまり、ルール通りに捉えるならば、実質、レースはもう。
終っているのです。
ですが、皆、あきらめず、必死にマシンの整備すすめます。
ヘタに要約すると、この感動が伝わらないので、本からそのまま引用します。
———————————
「くそ」
と中村良夫は思った。いろんなことに腹がたっていた。それ以上に、ここまできて何もしないでレ―スをあきらめるのは、どうしてもいやだった。レースで走るために長いあいだみんなで努力してきたのである。とくにザンドフールとからのメカニックたちの努力には、目ざましいものがあった。彼らは必要とあれば夜も寝なかった。また、ロニーバックナムも何とかニュールブルクリンクのタフなコースに慣れようとして、毎日何時間も慣熟走行をかさねてきた。ここで黙ってマシンをトランスポーターに積んで帰ったのでは、そうしたものすべてが無になるのである。
中村良夫は意を決し、ドイツ自動車連盟のレース部長のところへ行った。このドイツ・グランプリに出走申し込みをしたとき、すでに締切が過ぎていたのに特別のはからいで申し込みを受けつけてくれたのは彼だった。その親切をもう一度期待したのである。駄目でもともとであった。
中村良夫はレース部長室に行くと、彼に訴えた。
「われわれのマシンはエンジントラブル・トラブルで動けなくなった。われわれとしては、午後の公式予選の時間が切れるまでにエンジンを載せ替えて、何とか規定のあと一ラップを走れるようにしたい。しかしもしまに合わなかったときは、公式予選のあとに特別のセッションを設けて、われわれに一ラップを走るだけのチャンスを与えてもらえないだろうか」
すると、レース部長はしばらく考えたあとでいった。
「公式予選中に作業が終る可能性はどのくらいあるのかね?」
「その可能性はぜんぜんない」
と中村良夫は率直にいった。「しかしわれわれはぜんぜんない可能性を求めて、全員が必至で努力している。それだけは認めてもらいたい」
「それは分かっている。君たちが二日前にここへきてから、いかに組織立って立派に努力しているか、分かりすぎるほど分かっている」
ホンダF1チームがキリキリ舞いして車をいじっているのは、誰もがしっていたのである。それからレース部長は口をつぐみ、目をつぶって何もいわなくなってしまった。中村良夫が不安な顔をしていると、彼は目を開き、にっこり笑っていった。
「心配するな。わたしはどういう口実で他のチームにも納得させて君たちにチャンスを与えるのが最善か考えているんだ」
中村良夫は、不覚にも目頭が熱くなってどうしようもなかった。
———————————

1.5リッターF1最終戦メキシコ・グランプリ
ドライバー リッチーギンサーとチームを
初優勝へ導いた中村良夫監督
いかん、転記しながら、目に汗をかいてしまった・・・
可能性があろうがなかろうが、やりつくす!
自分もかくありたいなと思う次第です。